■第26回 「大学生が知っておくべき扶養のルールとバイト収入の限度額」|UNi+(ユニタス)

大学生がアルバイトをする際、扶養に関するルールや収入の限度額について理解しておくことは重要です。
扶養控除の対象から外れることで税金や社会保険料の負担が増える可能性があるため、自分や家族の負担を抑えるために知識を身につけておきましょう。
本記事では、扶養の基準となる収入の上限や、年収103万円や130万円の壁と呼ばれるポイントをわかりやすく解説。
自分の働き方や目指す収入に応じた対応策を考えるための基本情報をまとめましたので最後までチェックしてください。
大学生と扶養の関係とは?
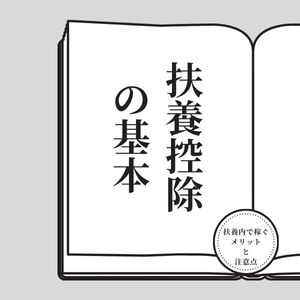 大学生がアルバイトをする際、親の扶養に入るかどうかは大事なポイント。
大学生がアルバイトをする際、親の扶養に入るかどうかは大事なポイント。
扶養のルールや収入上限を知らないと、思わぬ負担が発生することもあるため、しっかりと理解しておきましょう。
扶養控除の基本
扶養控除とは、親が一定の収入以下の扶養家族を持つことで、所得税や住民税の負担を軽減できる制度。
大学生の場合、年間のバイト収入が103万円を超えると、所得税の扶養控除対象から外れることになります。
さらに、130万円を超えると親が加入している健康保険の被扶養者からも外れる可能性が出てくるため、収入管理も必要に。
特に103万円や130万円の「壁」と呼ばれる収入ラインを超えた場合の影響については、事前に確認することが大切です。
親の扶養に入るメリットと注意点
親の扶養に入ることで、親の税負担が軽くなり、家計全体で見ても経済的な恩恵を受けることができます。
さらに、健康保険の被扶養者であることで、自身が保険料を支払わずに医療保険の恩恵を受けられる点も大きなメリットです。
しかし、収入を増やしすぎると扶養を外れるため、税金や社会保険料が自己負担になり、結果的に手元に残るお金が少なくなる場合も。
そのため、収入を調整しつつ、親の扶養内に収まるかどうかをよく考えて働く必要があるでしょう。
扶養内で働く場合の収入制限と「103万円の壁」について
大学生が親の扶養に入りながら働く場合、収入の上限に注意が必要です。
「103万円の壁」は特に重要な基準となります。
「103万円の壁」とは何か?
「103万円の壁」とは、年間の所得が103万円を超えると所得税の扶養控除の対象から外れるラインを指します。
この金額は給与所得控除と基礎控除の組み合わせによって決まっています。
103万円以下の収入であれば、所得税がかからないため、親の扶養に入ったままで税制上の優遇を受けられますが、103万円を超えると親の控除額が減少し、家計全体での税負担が増えることになります。
所得税がかからない扶養内の働き方
扶養内で所得税をかけずに働くためには、年間の収入を103万円以下に抑えることが基本です。
この制限を超えないようにするために、具体的な働き方として、まず勤務時間を調整することが重要です。
例えば、時給1,000円で働く場合、年間の勤務時間をおおよそ1000時間未満に抑えることで、収入が103万円を超えないように管理できます。
また、長期休みのある大学生であれば、短期のアルバイトを選んで特定の期間だけ集中的に働くことも効果的。
シフト制のアルバイトで働く場合は、月ごとの収入を把握し、必要に応じてシフトを調整してもらいましょう。
大学生のバイトと扶養の関係については以下の記事でも詳しく解説していますので確認してください。
■第27回 「大学生のバイトと扶養の関係!103万円・130万円の壁を徹底解説」
扶養から外れる収入ライン「130万円の壁」とは?
130万円を超える収入を得ると、親の健康保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入する義務が生じます。
「130万円の壁」の仕組みと社会保険の適用
「130万円の壁」とは、年間の収入が130万円を超えると親の健康保険の扶養から外れる基準を指します。
これにより、自身で国民健康保険や厚生年金保険への加入が必要になることがあります。この収入基準は、パートやアルバイトで働く学生にとって重要なポイントであり、年間の収入が130万円未満であれば親の健康保険の被扶養者として社会保険料を支払う義務が免除されます。
しかし、130万円を超えた場合、社会保険の負担が生じるため、給与の増加とともに手元に残る収入が減少するケースもあるのです。
130万円以上稼ぐ場合の影響と社会保険料の負担
収入が130万円を超えると、親の扶養から外れ、所得税や住民税に加えて、自身で社会保険(健康保険と厚生年金)に加入する必要があります。
毎月の給与から社会保険料が控除されるため、手取り収入が減少します。
例えば、40歳未満の場合、年間の社会保険料はおおよそ19万円程度かかることが一般的です。
また、所得税や住民税も発生し、これにより年収130万円の場合の手取りは108万8,000円ほどに減る可能性があります。
扶養を超えた場合に大学生が受ける影響
 扶養を超えると、税金や社会保険料の負担が発生し、手取り収入が減少するだけでなく、家計全体の負担にも影響を与える可能性があります。
扶養を超えると、税金や社会保険料の負担が発生し、手取り収入が減少するだけでなく、家計全体の負担にも影響を与える可能性があります。
税金や社会保険料の発生
収入が103万円を超えると所得税の課税対象となり、130万円を超えると親の健康保険の扶養からも外れ、社会保険料の支払いが必要となります。
健康保険料や厚生年金保険料が給与から天引きされるため、手取り額が大幅に減少することがあります。
収入は増えても実際に使える金額は意外に少なくなる場合もあります。
一方で、社会保険に加入することで将来的な年金の受給額が増加するメリットもあります。これらの点を踏まえ、収入計画や働き方を見直すことが大切。
大学生が扶養の枠を超えて働く場合は、短期的な負担増と長期的な保障のバランスをよく考え、慎重に収入を管理することが求められます。
扶養から外れたときの影響やメリット・デメリットについては以下の記事も参考にしてください。
■第28回 「大学生が扶養を外れるとどうなる?メリットとデメリットを徹底解説!」
扶養内で収入を抑えるためのバイト収入管理のコツ
扶養内で働くには、収入をコントロールすることが大切。
収入の上限を超えないよう、シフトの調整や勤務時間の管理しましょう。
シフト調整の工夫と収入管理方法
扶養内での収入を抑えるためには、シフトを柔軟に調整することが大切です。
例えば、繁忙期に集中して働きすぎると収入が急増し、扶養の基準を超えてしまうことがあります。
そのため、年間を通じてバランスよく働くよう心掛けると良いでしょう。
また、月ごとの収入を計画的に把握し、年度後半に上限に近づく場合は、勤務時間を減らすなどの対策を取ることが必要です。
学生が扶養内で働く為のおすすめバイトや収入官吏のコツについては以下の記事で解説しています。
■第25回 「大学生が扶養内で働く為のおすすめバイトと収入管理のコツ」
扶養範囲で働けるおすすめのバイト
扶養内で働きやすいバイトとしては、シフトの調整がしやすい短時間勤務のコンビニスタッフや、飲食店のホール業務などが挙げられます。
これらの仕事は、週ごとにシフトを変更できることが多いため、収入を管理しやすい特徴があります。
また、家庭教師や塾講師も時間あたりの収入が高いことから、効率的に収入を得られるかもしれません。
派遣バイトやイベントスタッフのように短期間で働ける仕事も、収入をコントロールしやすい点でおすすめ。
自身のスケジュールに合わせて柔軟に働ける職種を選び、扶養内で収入をうまく調整していきましょう。
扶養内で大学生活を充実させるためのバイトについては以下の記事も参考にしてください。
■第24回 「扶養内で大学生活を充実!おすすめバイト5選と注意点!」
年末調整と確定申告の基礎知識
年末調整や確定申告は、収入や税額を正確に把握するために重要です。
扶養内での調整や高額所得者の手続き方法を知っておきましょう。
扶養内での年末調整の仕組み
年末調整とは、1年間に支払われた給与や所得税額を再計算し、払いすぎた税金を調整する手続きです。
扶養内で働く大学生も対象となることがあります。
年末調整は単純に年収基準だけで自動的に免除されるわけではありません。
毎月の給与から所得税が源泉徴収されている場合でも、年間の収入が103万円を超えないなら、年末調整により所得税が還付されることがあります。
重要なのは、扶養控除等申告書を提出すること。
これにより、所得税の源泉額が月ごとに調整され、基準額以下の収入では税金が引かれない場合もあります。
しかし、収入が月ごとに変動し、ある月に収入が8万8,000円以上になった場合は、源泉徴収される可能性があるため注意が必要です。
企業側は年末調整を行い、源泉徴収票を交付する義務がありますので、扶養控除等申告書を提出している方は、収入にかかわらず年末調整の手続きを受けることが可能です。
扶養内で働く方は、年末調整を正しく理解し、税金負担を最小限にするために必要な手続きをしっかりと行いましょう。
所得が多い場合の確定申告の必要性とその手順
年間の所得が扶養範囲を超える場合は、年末調整だけでは不足し、確定申告が必要となることがあります。
確定申告は毎年2月中旬から3月中旬に行われ、自身の所得を申告し、税金の過不足を精算するための手続き。
必要な書類としては、給与明細や源泉徴収票、控除を受けるための証明書などがあります。オンラインでの申請も可能で、e-Taxを利用すれば手続きがスムーズに進みます。
確定申告を行うことで、所得税や住民税の正確な負担額が確定するため、所得に応じた適切な税額を負担することができます。
所得が多い場合は、確定申告を忘れずに行い、税務手続きを適切に進めましょう。
まとめ
扶養内で働く大学生やパート・アルバイトの方が知っておくべき年末調整や収入管理のポイントを解説しました。
年収103万円や130万円の壁といった収入ラインを理解し、税金や社会保険料の負担を最小限に抑えることが重要です。
また、シフトの調整や扶養控除等申告書の提出を適切に行うことで、税制上の恩恵を受けることができるでしょう。
